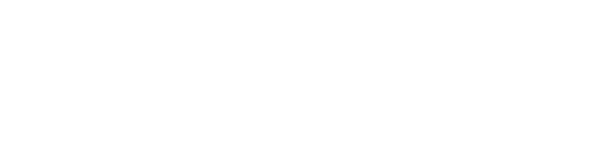最近は外国から日本へ働きに来てくださる方々も多くなってきました。当法人も例外ではなく、アジア各国から日本にお仕事をしに来られた職員も増えてきました。なないろでも、ミャンマーから来てくれた2人の男性職員が一緒に働いています。
なないろで働いている2人は、2024年度から日本に来ています。来日当初からかなり日本語が上手で、ゆっくり話せば日本語オンリーでも十分伝わっていました。1年以上経った今では、ネイティブスピードで話しかけても全部理解してくれるくらい日本語が上達しています!
とはいえ、私たち日本人にとっても難しい日本語。違う言語を使用する国から来た彼らにとってはかなり難しい。しかし今後、ケース記録に利用者さんのご様子を記録したり、普段おこなっている支援についてより深く知ってもらったりするとなると、簡単な文だけでなく、もう1ステップ上の日本語を使っていきたい。ということで、ミャンマーから来た2人のサポートを色々としてくださっている職員が、彼らに向けて日本語の勉強会を開催してくれました。

この勉強会では、日本語とミャンマー語で作成した資料を使い、支援の現場で使われる日本語にフォーカスして学びを深めていきます。「現場密着型日本語教室」というイメージでしょうか。同じ現場で毎日共に働いている職員同士だからこそ、できる取り組みかもしれません。
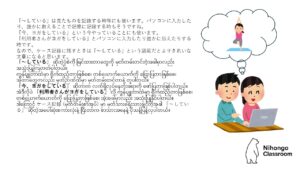
初回となる今回のテーマは「日本語の語尾」について。利用者さんのご様子を記録していくとき、「○○した」ではなく「○○している」と記載します。その違いはなんなのか、なぜ「○○している」なのか?改めて考えると、日本語って難しいなぁと実感します。
(文:西山)